政府はなぜ「ラピダス」のような会社を増やさないのか…日本が「半導体シェア世界1位」を奪還するために必要なこと
プレジデントオンライン / 2024年5月13日 9時15分
■AIに不可欠なHBM分野で韓国が独走中
ここへきて、世界的な生成AIの急成長に伴い、世界の半導体産業に重要な変化が出ている。具体的には、中央演算装置(CPU)から“画像処理半導体(GPU)”へ需要は急速にシフトしている。メモリー半導体分野で、NAND型フラッシュメモリーの需要回復に時間がかかる一方、AIに不可欠な“広帯域半導体(High Bandwidth Memory=HBM)”の需要が急拡大している。
この変化は、わが国の半導体産業にとっても重要な意味を持つ。現在、わが国にはHBMを生産できる企業が見当たらない。世界のHBM市場で独走状態にあるのは、韓国のSKハイニックスだ。メモリー分野で世界トップのサムスン電子、米マイクロンテクノロジーも相次いでHBMの研究開発や量産体制の強化を急いでいる。
今後、GPUとHBMを組み合わせ、より効率的にAIの学習を試みる企業は増える。それに伴い、半導体製造プロセスも変化する。回路の線幅をより細くする“微細化”に加え、複数の半導体を組み合わせる“チップレット方式”の重要度が高まる。
■半導体需要はPC、スマホ向けからAI向けへ
需要に合わせて高性能なチップセットを、迅速に供給する体制を確立することが重要になっている。部材の供給や半導体製造装置の精度など、わが国が世界経済に果たす役割は増えるだろう。素材、精密機械などの製造技術を使って、GPUに加えHBMでも国内企業による量産体制の確立が実現するか否か、中長期的なわが国経済の成長に重要だ。
2022年11月、米オープンAIの“チャットGPT”の公開をきっかけに、世界の半導体業界の状況は大きく変わった。当時、テレワークの一巡などでパソコン向けのCPU、スマホ向けのチップやメモリーの市況は悪化した。一方、AI分野の拡大で最先端のGPU、HBMの需要が急増し始めた。
GPU分野で競争力を急速に高めたのが米エヌビディアだった。同社は、台湾積体電路製造(TSMC)の3ナノ(ナノは10億分の1)メートルの製造ラインを使って、人工知能の深層学習に使われるGPUの供給体制を強化した。
GPUが役割を存分に発揮するため、データ転送速度の高いメモリーチップ需要も高まった。そのニーズにこたえたのが、2013年にHBMを世界で初めて生産した韓国のSKハイニックスだった。
■先行者利得を獲得したSKハイニックスの戦略
エヌビディアとSKハイニックス、TSMC、米韓台の主要半導体企業は連携を強化し、GPU、HBMの分野でAI関連需要を獲得した。ファウンドリ分野でTSMCを追いかけるサムスン電子、同分野で遅れた米インテルのシェアは低下した。
需要が変化したため、メモリー分野でのHBMの重要性は高まった。従来、パソコンやスマホのメモリー半導体は、画一的な製造手法で価格競争力がシェア獲得に重要な役割を果たしてきた。
それに対しSKハイニックスはエヌビディアのニーズに対応することを優先し、HBM市場で先行者利得を獲得した。世界の半導体産業のビジネスモデルは、ウィンドウズ搭載PC用の画一的なチップから、主にAI向けカスタマイズへシフトしたのである。
多様なニーズに対応するため、他企業とのアライアンスやコンソーシアムの重要性も高まっている。製造工程での微細化に加え、複数のチップを一つにまとめる“チップレット生産”を重視する企業も増えている。
■既存事業を重視する企業は出遅れている
AI分野の加速度的な成長で、GPU、HBMの供給は需要に追い付いていない。GPU分野で、AMDやインテルも開発体制を強化した。それでも、エヌビディアの優位性は高い。1月~3月期の決算を見ると、AMDはゲーム向け半導体事業が収益の足枷になった。インテルはファウンドリ事業の遅れなどが業績を圧迫した。
いずれも、既存事業が先端分野の需要急増への対応を難しくした。それはHBMにも当てはまる。HBMの発明者であるSKハイニックスは、より有利に需要を獲得している。同社によると、2024年のHBM受注枠は埋まり、2025年もほぼ埋まった。サムスン電子とマイクロンテクノロジーも8層から12層への移行を急いでいるが、エヌビディアとの関係強化でSKハイニックスがリードしている。
AI分野の需要の獲得をめざした競争も激化する。特に、中国勢はGPU、HBM両分野で研究開発と生産体制を急速に強化している。通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)は政府の補助を受けてGPU、HBMの開発を強化し、2026年からの生産を目指しているようだ。ファーウェイは上海に半導体製造装置の研究開発拠点も設ける計画だという。
■中国は一帯一路沿線にデータ経済圏を確立か
“中国のエヌビディア”と呼ばれる、中科寒武紀科技(カンブリコン)もGPU開発を強化している。中国のDRAM大手、長鑫存儲技術(CXMT)もHBMの製造を準備しているようだ。同社は、米国の規制対象でない半導体製造装置の確保を急いでいるという。
2021年から2022年にかけて、世界で出願された半導体関連の特許件数で中国はトップだった。ソフトウェア面で中国半導体業界の成長意欲は高い。中国政府はバイドゥなどの生成AI開発支援も強化し、経済と社会への統制を強めようとするだろう。さらに、AIチップ、サーバーなどを一帯一路沿線地域に輸出し、中国中心のデータ経済圏の確立を目指すことも考えられる。
AI分野の成長の加速で、GPU、HBM、チップレット生産に対する需要は増加し、競争も激化するだろう。先端分野で米中の対立も先鋭化しそうだ。AIチップ、製造装置、チップレットに使う素材分野で、米国政府が対中制裁や輸出規制を一段と強化する可能性は高い。
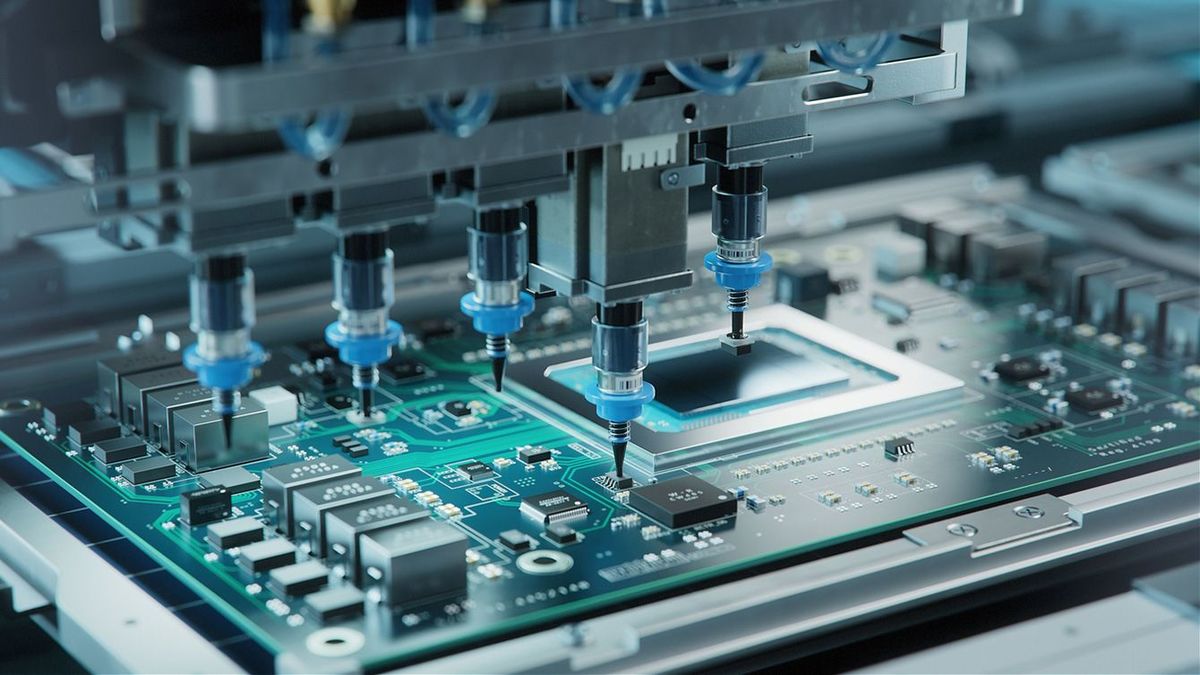
■日本経済の将来はラピダスの動きにかかっている
わが国がAI分野の需要を取り込むカギは、GPU、HBM、チップレット生産に必要な部材、製造装置分野にある。わが国の関連企業の競争力は世界的に高い。政府と企業はそうした優位性を生かし、GPU、HBMの国内生産を目指すことが必要だ。それは、中長期的なわが国経済の成長に寄与するはずだ。
特に、HBM分野で対応の強化は急務だ。現時点でわが国に、HBMを生産できる企業は見当たらない。2025年前半までにラピダスは、2ナノメートルの回路線幅を持つロジック半導体の試験生産を行う予定だ。米IBMや蘭ASMLなどはラピダスと協業を強化する。補助金政策の運用も含め、ラピダスの意思決定のスピードが、新しいAIチップの創出を支えるとの期待もある。
■日本でも新型メモリー企業の創設が待たれる
一方、HBMはそのレベルまで至っていない。GPUとHBMをセットで活用することがAI分野の成長実現に欠かせない。わが国で新型メモリー企業を創設・育成する意義は大きい。ラピダスを例にすると、まず民間企業の共同出資で新しいメモリー半導体メーカーを設立する。事業戦略を迅速に立案し、政府は工場建設などを支援する。内外のAI、半導体関連企業と関係を強化し、受託製造ニーズを取り込む。
既存の企業を活用する手もある。SKハイニックスはキオクシアにHBMの生産協業を打診したようだ。政府による補助金支給への期待、部材メーカー等との関係強化があるだろう。関連企業の事業戦略として、海外HBMメーカーの要請に迅速に応えることは先端分野での需要獲得に重要だ。あるいは、大学発のスタートアップ企業が新型AIチップを開発し、生産を国内企業に委託する展開も考えられる。
GPU分野で独走態勢のエヌビディアでさえ、投資に失敗したことはあった。それでも、創業経営者の諦めない姿勢が、GPU創出、AI分野の需要獲得を支えた。戦略物資として半導体の重要性が高まる中、そうした企業のリスクテイクが難しくなると、経済成長に負の影響があるだろう。わが国でのGPU、HBMなどの生産に向け、政府が民間企業のリスクテイクをより強力にサポートする必要性も高まっている。
----------
多摩大学特別招聘教授
1953年神奈川県生まれ。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社ニューヨーク本社出向。みずほ総研主席研究員、信州大学経済学部教授、法政大学院教授などを経て、2022年から現職。
----------
(多摩大学特別招聘教授 真壁 昭夫)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
韓国SKハイニックス、株価20万ウォン初めて突破…NVIDIAの好業績に支えられ
KOREA WAVE / 2024年5月24日 9時0分
-
アングル:中国2社、AI用メモリーの生産開始 外国依存低下の取り組み前進
ロイター / 2024年5月16日 11時17分
-
NVIDIA急伸に「追い風受ける日本企業」はここだ 沸騰する半導体市場の最前線をQ&A形式で解説
東洋経済オンライン / 2024年5月14日 7時20分
-
政府支援の光と影「半導体人材」が増えぬ深刻事情 東大・竹内氏「AI半導体で日本に勝ち筋はある」
東洋経済オンライン / 2024年5月14日 7時0分
-
AIの可能性を再定義するHBM、その構造を理解する
マイナビニュース / 2024年5月10日 7時20分
ランキング
-
125年末まで減産延長=油価下支えへ―OPECプラス
時事通信 / 2024年6月2日 23時29分
-
2「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点
東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分
-
3なけなしの貯金と「年金月14万円」で暮らす70代女性、冷房代が払えず「“タダで涼める”スーパーへ避難生活」が続くも…「店長のひと言」で人生が一変したワケ
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月29日 9時0分
-
4PIAAからヘッド&フォグ用LEDバルブ 6000K「超高輝度」シリーズ・5製品が登場
レスポンス / 2024年6月2日 10時30分
-
5万博「経済効果」は2.9兆円? 国と民間、大阪府市で異なる予測の数字なぜ
産経ニュース / 2024年6月2日 18時43分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










