予算が一気に3倍増で「宇宙バブル」の様相…3000億円を50人で当面差配する「岸田政権の宇宙戦略」は大丈夫か
プレジデントオンライン / 2024年5月17日 16時15分
■政府基金は無駄遣いの温床になってきた
政府が新設した「宇宙戦略基金」が動き出す。
スタートアップ(新興企業)、企業、大学の技術開発や研究に補助金などを出し、10年間で総額1兆円規模の支援をするというものだ。
全体をとりまとめる内閣府が、4月末に支援対象22テーマを発表した。費用を100%補助するものや、一企業に500億円を超える支援をする場合もある。
「これまでにない思い切った支援」と宇宙業界は歓迎するが、内容を見ていくと支援企業の選定方法や責任の所在がはっきりせず、支援金が悪用されたり国への依存が強まったりする懸念もある。
内閣府の発表によると、第一弾として、文部科学省が1500億円、経済産業省1260億円、総務省240億円の計3000億円を出し、「宇宙輸送」「衛星」「探査」の3分野22テーマの技術開発や研究を支援する。
基金は宇宙航空研究開発機構(JAXA)に設置。JAXAが基金の運用、支援先の選定、技術支援、全体のマネジメントなどを担う。7月からJAXAが公募を始め、今年度内に支援先を選定する予定だ。
政府基金は2000年代に入ってから各省庁が競うように設立した。政府予算のように1年ごとに計上する必要がなく、複数年分をまとめて計上して使えるなど自由度が高いためだ。一方で国会などの監視の目が届かず、無駄遣いの温床になる問題が起きている。
■3000億円が3倍に膨れ上がる「宇宙予算バブル」
政府は4月22日に、基金の一部事業を廃止し、約5400億円を国庫に返納すると決めた。
内閣府が、宇宙戦略基金の支援策を公表したのは、その4日後。逆風の中でも新設できた背景には、宇宙を取り巻く環境が大きく変化していることがある。
安全保障、防災、地球観測、通信など、世界で宇宙開発や利用がさかんになり、市場規模も拡大している。担い手も、国から民間へと移っている。
「1年ごとの予算に縛られたり、JAXAが企画・設計して大手メーカーに仕事を発注したりする硬直したやり方では、世界との競争に勝てない。予算も少なすぎる」――。政治家、宇宙業界、政府などからそんな声が巻き起こった。
米国は、米航空宇宙局(NASA)や国防総省などの政府機関が、スタートアップなどに資金を提供して、技術開発や研究を推進している。日本も宇宙基金を作り、そうしたやり方を目指そうとしている。
宇宙基金を足すと、今年度の宇宙予算は約8900億円になる。宇宙予算は、3年前から少しずつ増えてきたが、長年にわたって約3000億円台の横ばいが続いた。今年度は一気に拡大し、まさに宇宙予算バブルのような状況だ。
■宇宙基金とは別にスタートアップ支援もしているが…
それにしても額が大きい。
経産省は、多数の衛星を一体的に運用して、通信や観測に使う「商業衛星コンステレーション構築加速化」に約950億円を投入する。最長7年間支援し、対象は3件~5件。スタートアップや中小企業の場合、一企業に最大533億円を支援することも見込んでいる。
文科省は、高頻度で詳細に衛星から地球を観測できる「高分解能・高頻度な光学衛星観測システム」をテーマのひとつに設定。1件を対象に最長5年間で約280億円を提供する。
総務省は、「衛星量子暗号通信技術の開発・実証」で、1件を対象に5年程度で約145億円の支援をする。
目標の10年1兆円を目指し、政府は今後も基金を積み増していくという。
技術開発や研究が進展したり、ビジネス化に成功したりするなどの効果もあるだろう。だが、基金の原資が国民の税金であることを考えると、懸念すべき点も目に付く。
ひとつは、宇宙基金を出した3省庁の支援先が重なったり、政府の他の基金や予算と重複したりして、無駄を招かないかという点だ。すでにその兆候が見える。
最近の政府の産業振興策は、スタートアップ支援がブームのようになっている。
文科省や経産省は、宇宙戦略基金とは別の「中小企業イノベーション創出推進基金」に、資金を提供し、スタートアップ支援をしている。
■ホリエモンロケット、カイロス、アストロスケールも
例えば文科省は昨年9月に、「民間ロケットの開発・実証」事業として、実業家・堀江貴文氏が創設した「インターステラテクノロジズ」、東京理科大発の「スペースウォーカー」、元経産省官僚が立ち上げた「将来宇宙輸送システム」の3社にそれぞれ、今年9月までに最大20億円の交付を決めた。今年3月に初打ち上げに失敗したカイロスロケットの「スペースワン」にも最大約3億円の交付を決めている。
ほかにも、宇宙ゴミ対策に取り組む「アストロスケール」に、来年1月までに最大約27億円を交付する。
経産省もこの基金を使って、昨年10月に、月面着陸を目指す「アイスペース」に最大120億円、小型観測衛星システムに取り組む九州大発の「QPS研究所」に最大41億円など、計9社への補助金交付を決めた。
基金ではないが、防衛省も宇宙スタートアップと積極的に契約を結んでいる。今年2月に、「QPS研究所」と、56億4900万円で実証衛星の試作を契約した。3月には、ロケットの能力向上の研究として、「スペースワン」とも85億円で契約した。防衛省は、「今後もスタートアップを含む民間事業者と連携しながら、民生先端技術の積極的な取り組みを図っていく」という。
ほかにも、JAXAとの共同研究などの形で支援を受けているスタートアップや企業は多い。
■チェックする側は現在40人程度しかいない
日本の宇宙スタートアップは100社程度と言われるが、アクティブに活動をしているところは、限られている。同じところにお金が集中し、「使いきれなくなるのではないか」との懸念や苦言が、政府や産業界、学術界からも出ている。
2つ目は、適切な支援先を選ぶことができるかどうかだ。
基金事業の巨費に目をつけて、詐取しようとする人や組織が現れる可能性もある。支援対象の企業や大学だけでなく、下請け、取引相手、共同研究先などを含めてひとつひとつ確認し、日本の税金や技術が、思わぬ組織や個人に流れてしまわないように注意する必要がある。
きちんとチェックできる体制づくりが欠かせないが、その役目を担うJAXAの担当者は、現在約40人。JAXAによると、金融関係者、政府や自治体からの出向者など、さまざまな人員を集めて順次拡充し、当面は50人程度を目指すという。公募を始める7月には担当組織を整えるため、この時に「かなり人員が増えるのではないか」(政府関係者)と言われている。
だが、第一弾の基金だけでも、JAXAの昨年度の予算の1.4倍もある。ふさわしい対象を選び出し、技術開発を成功させ、実用化、産業化などの成果へと結びつけることができるかどうかの判断は、かなり難しい。どのような陣容でのぞむかという全体像を示さずにスタートを切った形になっていることも、懸念を高める一因になっている。
■日本人の税金が海外企業に使われる?
3つ目は、基金の巨費に見合うように、日本の技術力や研究力を向上させることができるかどうかだ。
内閣府によると、海外の企業も、日本法人を作っているなどの条件を満たせば宇宙基金に応募できる。日本法人がなくても、宇宙基金を得た日本企業との共同研究が可能だ。海外の大学も、宇宙基金を得た日本の大学と共同研究できる。
内閣府の文書では「支援対象者が同盟国・同志国との国際共同研究・実証等を行うことを可とする」としているため、そうした事例が多々出てくるのではないかと思われる。国際協力は重要であり、ビジネスチャンスや成果拡大につながる可能性があるが、あまり増えすぎると、宇宙業界以外の人々から「なぜ日本国民の税金で海外企業を支援するのか」という批判も出てくるだろう。
本当に日本にとってプラスとなるかどうか、精査が必要だ。それもJAXAの役割だという。
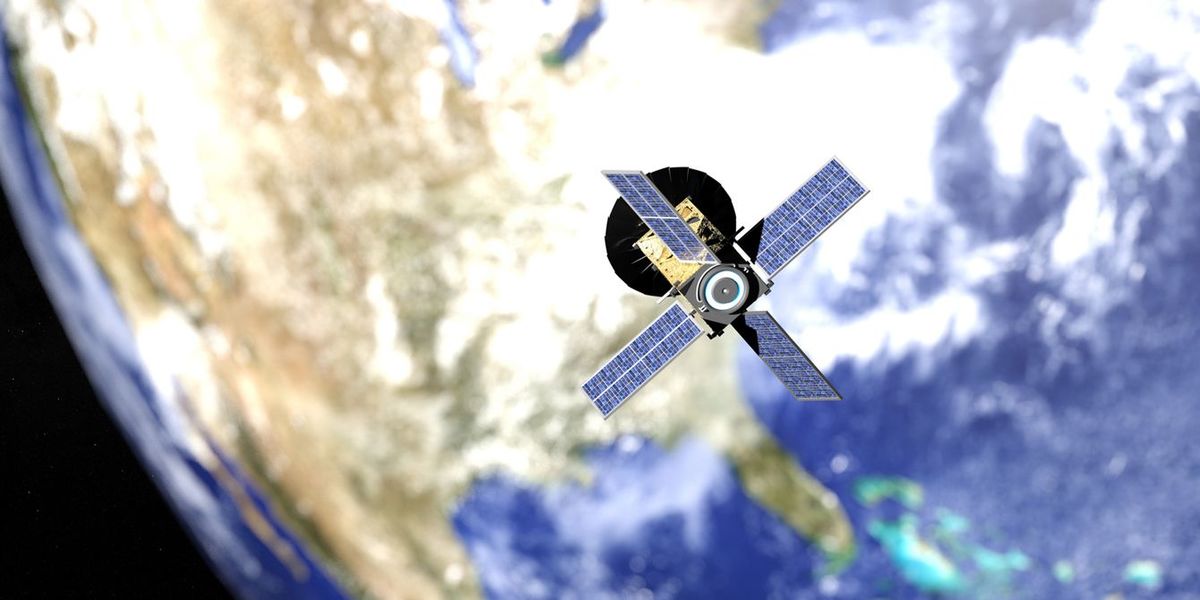
基金の目的は、実施した技術開発や研究の成果を、ビジネスにつなげたり、社会で使われるようにしたりすることだ。
かつて、JAXAが開発した技術は、あまり産業化や実用化につながらないと指摘され、「技術開発のための技術開発」と批判されていた。宇宙基金による技術開発も、企業まかせにするだけだと、技術開発だけで終わってしまう心配がある。目的実現に向けてJAXAがどこまで支援すべきかも大きな課題だ。
■米国では支援金太りしたスタートアップも
事業が長期間にわたることへの不安もある。技術開発がうまくいかないケースも出てくるだろうし、10年もたてば世の中も変わる。できあがる頃には時代にそぐわなくなっていることもある。
内閣府は、「年に1回」「開始から3年目」などの節目に評価を行い、JAXAが中止などを検討するという。だが、宇宙事業では、これまでもいったん始めるとやめられずにずるずると続けることが何度もあった。評価をきちんと機能させるように、JAXAや資金を出した省庁などの責任をもっと明確にする必要があるだろう。
お手本にした米国では、最近は政府のスタートアップ支援の行き過ぎが、産業界などから問題視されている。NASAや国防総省など政府のお金を獲得し続けることが目的化し、自らビジネスで成功しようという意欲が薄れてきているという。民間の投資会社からも、投資を回収できなくなるという懸念の声が出ている。日本でも、同様の心配がある。
■「貧乏研究室」が大量発生した失敗が思い出される
基金の原資は税金だ。責任の所在を明らかにし、無駄な使い方を防止することが必要だ。支援する理由、支援先の下請け企業、共同研究先なども含めて、どこにどれだけお金が流れているか、技術開発がどこまで進み、どんな成果を上げているのか、などについて、国民にもわかるようにデータベースを作って公開するなど、透明化をはかることが必要ではないか。
2000年代初頭の科学技術政策で、研究予算の「選択と集中」を推進した結果、予算が集まりすぎて使いきれない研究室が生まれた。いろいろな役所や政府関連機関が、縦割りのままバラバラに、同じ研究者に重複して研究費をつけたことが原因だった。
一方で、予算に事欠く研究者が多数生まれ、日本の研究力低下につながったと見られている。
同じことを宇宙基金でも引き起こさないためのシステム作りが求められる。
政府基金への批判渦巻く中でのスタートを、内閣府も気にしているのだろうか。「国民の理解は不可欠」と強調し始めた。今まであまり興味を示してこなかっただけに、大きな変化だ。
内閣府は「(宇宙予算が)3000億円の時代から、8000億円時代にギアチェンジした。今まで以上に情報発信をすべき」と言い、宇宙開発を担う産業界などに「宇宙開発の成果の意義」を発信するよう求め出した。
発信だけにとどまらず、宇宙戦略基金を大きな「ブラックボックス」にしないための、透明化の工夫も求められる。
----------
科学技術ジャーナリスト
東京大学文学部心理学科卒業後、読売新聞入社。婦人部(現・生活部)、政治部、経済部、科学部、解説部の記者、デスク、編集委員を務めた。宇宙開発、科学技術政策、研究、ICTなどの科学技術分野を35年以上にわたって取材・執筆している。1990年代末のパソコンブームを受けて読売新聞が発刊したパソコン雑誌『YOMIURI PC』の初代編集長も務めた。現在はフリーで活動している。
----------
(科学技術ジャーナリスト 知野 恵子)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
地球観測衛星は元日の能登半島地震をどう見たのか? - 衛星リモセンの必要性
マイナビニュース / 2024年5月25日 7時3分
-
LAND INSIGHTが経済産業省の衛星データ無料利用事業者に採択
PR TIMES / 2024年5月23日 14時15分
-
天地人、sorano me、慶應義塾大学、JAXA、 「衛星利用ビジネス検定」の開発に着手 ~衛星データを価値に変換できるスキルを磨く~
PR TIMES / 2024年5月23日 13時40分
-
「経済安全保障重要技術育成プログラム」で長距離物資輸送用無人航空機技術の開発・実証に着手
PR TIMES / 2024年5月22日 12時45分
-
「国家予算114兆円」がピンとくる人は何が違うか…「大きな数字」が一瞬で身近な数字に変わる「魔法の計算式」
プレジデントオンライン / 2024年5月11日 15時15分
ランキング
-
1【速報】今月開始の定額減税「評価しない」が60% 6月JNN世論調査
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月2日 22時57分
-
2「検証してもらわないと無駄死に」新型コロナワクチン接種後に夫が難病を発症し死亡 集団訴訟へ参加を目指す妻【大石が聞く】
CBCテレビ / 2024年6月2日 6時2分
-
3東京・港区長選、前区議の清家愛氏が自公推薦の現職ら破り初当選…自民は目黒区長選に続き敗北
読売新聞 / 2024年6月3日 0時35分
-
4「サンドバッグのように扱われた末に人生を終えた」検察が糾弾 遺体に20か所以上の骨折 隣人暴行死の罪に問われた男が記者に語った言葉「愛着に似たような気持ち」「誰かと一緒にいたかった」6月5日判決【後編】
MBSニュース / 2024年6月2日 15時6分
-
5百田尚樹氏 日本保守党の都知事選見送りで批判続出…「見損なった」「カネ使えに」の声に回答
東スポWEB / 2024年6月2日 19時54分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











